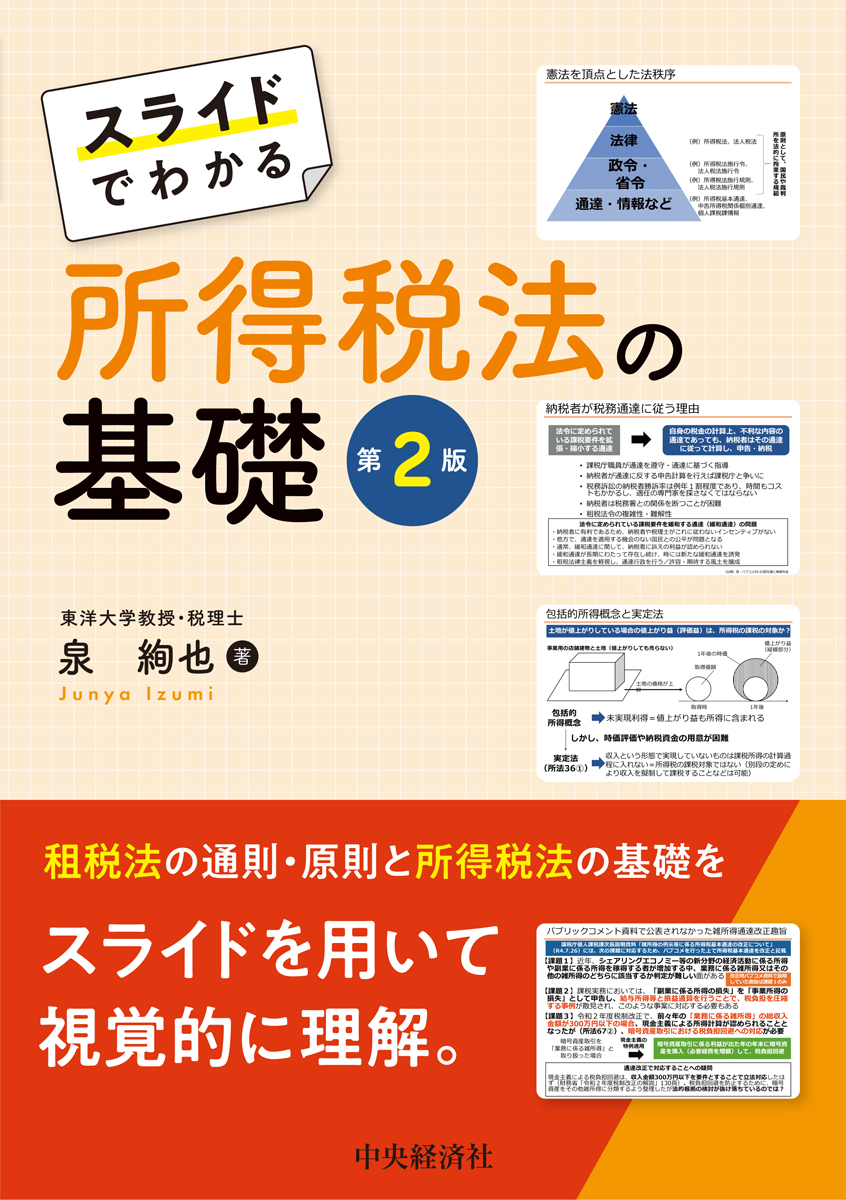本記事の紹介
【判決】不動産購入による為替差益にも課税:東京地裁令和7年2月5日判決
不動産取引による外国為替差益が「所得」として課税対象となるかが争点となった本判決では、外貨による不動産購入時における為替差益の実現性や、外貨の取得原価の算定方法が詳細に論じられました。
📌 主なポイント:
- 📈 外貨を用いた不動産取得により「経済的利得が確定」したとし、雑所得として課税すべきと判断
- 💱 外貨の取得価額の計算方法としては、暗号資産のような個別法の適用は否定され、総平均法に準ずる方法が妥当とされました
本件は、暗号資産税制との類似性を意識した主張が展開された点でも注目され、外貨・不動産取引における課税実務の参考資料となる判決です。
この記事のポイント
外貨建不動産購入による為替差益への課税と、外貨の取得原価算定方法(総平均法vs個別法)が争われた東京地裁令和7年2月5日判決を解説します。裁判所は、暗号資産の個別法の流用を否定し、総平均法に準ずる方法が妥当と判断しました。
外国為替差損益の課税関係が争点となる事案がいくつか出てきております。以下で紹介する東京地裁令和7年2月5日判決は、暗号資産の規定を用いた解釈論が展開されていますが、黄色の下線部分や本件の結論について、暗号資産ではなく外貨への個別法の適用を考えた場合に、個人的には別の解釈論もあるかなと考えています。他方で、暗号資産の個別法に関する議論の参考にもなるでしょう。
事案の概要
本件において、原告は、複数の預金口座において外国通貨(外貨)であるドル(米国ドル)及びユーロを保有していたところ、平成29年から平成30年にかけて、米国に所在する不動産をドル建てで購入するなどの複数の外貨建取引を行った。原告は、これらの取引につき、為替差益に係る所得はないとの前提で平成29年分及び平成30年分(本件各年分)の所得税等の確定申告を行ったが、麻布税務署長は、それらの外貨建取引につき為替差益が生じており、当該為替差益が雑所得に該当するとして、本件各年分の所得税等について各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分をした。
本件は、原告が、上記各処分が違法であると主張して、各更正処分の一部及び各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
争点
(1) 本件各不動産取引によって原告に為替差益に係る所得が発生し、実現したといえるか(争点1)。なお、原告は、本件外貨建取引のうち本件各不動産取引以外の各取引については、原告に為替差益に係る所得が発生し実現したこと及びこれが雑所得に当たることを争っていない。
(2) 為替差益の額を算定する際の外貨の取得時の円換算額の算定方法(争点2)
裁判所の判断
1 争点1(本件各不動産取引によって原告に為替差益に係る所得が発生し、実現したといえるか)について
(1) 為替差益に係る所得の把握において基準とすべき通貨について
ア 所得税法は、包括的所得概念を採用し、およそ人の担税力を増加させる経済的利得の全てを所得として構成するものとしているところ、外貨の為替レートの変動に基づく利益である為替差益も、人の担税力を増加させる経済的利得に当たるから、所得を構成するものといえる。
イ また、為替差益による所得を把握するためには、対象となる貨幣価値を基準となる通貨単位で測定する必要があるところ、所褥尋税法が我が国における法定通貨である邦貨(円)を基準として課税の範囲や税額の計算方法を定めていることや、同法57条の3第1項が外貨建取引の金額の円換算額は当該外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場により換算した金額として所得の金額を計算する旨規定していることなどからすると同法は、邦貨を基準として(すなわち、円換算することにより)、所得を測定することを当然に予定しているといえる。
したがって、為替差益による所得の把握においても、邦貨を基準とすべきであり、外貨を円換算することによってその所得を把握するのが相当である。
ウ、この点に関し、原告は、外貨建取引について邦貨を基準として為替差益に係る所得を把握することは当事者間の意思に反する、私法上の法律関係に抵触するなどと主張するが、課税の基準とすべき通貨をどのように定めるかは、取引の当事者の意思に委ねるべき性質のものではないし、また、邦貨を基準として為替差益に係る所得を把握したとしても、当該外貨建取引に係る契約内容に何ら変更等が生じることはなく、私法上の法律関係に抵触するものではないから、原告の主張には理由がない。
(2)為替差益に係る所得の発生ないし実現について
ア 為替差益につき、「収入すべき金額」(所得税法36条1項)に該当するためには、当該為替差益に係る経済的利得が何らかの形で実現することが必要である。例えば、単に外貨を保有し続けている状況において、為替レートの変動により当該外貨につき為替差益が生じたとしても、そのことだけでは、当該為替差益は所有資産の価値の増加(評価差額)にすぎず、未実現の利得であって、「収入すべき金額」に該当しない。
もっとも、当該外貨につき為替差益が生じている状態において当該外貨を用いて不動産等の資産を購入した場合、すなわち、当該資産の取得等のために払い出された外貨の払出時における円換算額から当該外貨の取得時の円換算額を控除した差額が正である場合には、当該外貨が当該資産に置き換わったことにより、当該為替差益に相当する経済的価値が確定し、所得として実現したといえる。仮に当該資産の購入時に当該外貨を新たに取得して(すなわち、その時点で円を当該外貨に両替して)当該資産を購入する場合には、当該為替差益を含む金額の円が必要となるのであり、外貨は当該為替差益分を含む経済的価値を有し、その価値によって当該資産を購入したと認められることからも、上記のように、当該為替差益に相当する経済的価値が確定し、所得として実現したということができる。
したがって、当該為替差益は、「収入すべき金額」に該当する。
この点に関し、原告は、外貨建借入金について同一の金融機関、同一の通貨、同一の金額等で借換えを行う場合には為替差益に係る所得を認識しないとした国税不服審判所平成28年8月8日裁決(甲11) や、外貨建
債券の償還の場面で券面額と同一の金額が同一の外貨で支払われる場合につき為替差益に係る所得を認識しないとした国税庁の質疑応答事例(甲8)等を挙げ、資産状況に実質的な変化がない場合は、為替差益に係る所得は実現しないとした上で、外貨で外貨建ての不動産を購入する場合には、当該不動産は取引後も引き続き為替変動リスクを負っているのであるから、資産状態に実質的な変化はないなどとして、所得は実現していない旨主張する。
しかし、上記裁決及び質疑応答事例に係る各事例は、各取引の前後において、資産の保有形態等に形式的な変化はあるものの、当該資産が同ーの為替変動リスクにさらされているという状態に変化はなく、実質的な変化がないと評価できるものである一方、不動産は、周辺の地価や取引相場、物価の変動等による価値の変動が生じ得るものであり、外貨(為替変動リスク)から独立した価値を有しているから、外貨が不動産に置き換わったことは、.資産状態に実質的な変化がないとはいえない。
したがって、外貨で不動産を購入する場合と、上記裁決及び上記質疑応答事例に係る各事例とを同列に考えることはできない。
ウ また、原告は、①企業会計基準である本件実務指針(甲14) の取扱いや、②所得税基本通達57の3-2の注書きの4の規定を根拠として、当初から資産の購入を予定して借入れを行い、借入れ後に資産を購入する場 合には、同一通貨ベースでの連続した一つの取引と考えることができるから、当該取引による為替差益に係る所得は実現していない旨主張する。
しかし、上記①については、法人税法は、収益の額等につき、別段の定めがある場合を除き、一般に公正妥当と認められる会計処埋の基準によるとしている(同法22条4項)のに対し、所得税法には同様の規定は置かれておらず、本件実務指針の取扱いが所得税法の法解釈を拘束する根拠はないというべきである。
そして、上記②については、所得税基本通達57の3-2の注書きの4は、「本邦通貨により外国通貨を購入し直ちに資産を取得し若しくは発生させる場合の当該資産、又は外国通貨による借入金に係る当該外国通貨を直ちに売却して本邦通貨を受け入れる場合の当該借入金については、現にその支出し、又は受け入れた本邦通貨の額をその円換算額とすることができる。」と定めるところ、これは、外貨建取引の直前又は直後において外貨と邦貨との交換がされた場合には、一般に、為替差損益がほとんど発生していないことを踏まえ、簡素化の観点から、実際に外貨と交換した邦貨の額を円換算額とするとの例外的な取扱いを認めたものと解され、本件各不動産取引のように、取引の直前又は直後において外貨と邦貨との交換がされていない事例において参考になるものではない。
(3) 本件各不動産取引について
本件各不動産取引は、本件口座に保有していたドルを用いて外貨建取引により不動産を購入する取引であるところ(前提事実(3))、上記(1)、(2)において説示したとおり、仮に各取引時において為替差益が生じている場合、すな’わち、本件各不動産の取得等のために払い出されたドルの払出時における円換算額から当該ドルの取得時の円換算額を控除した差額が正である場合は、当該差額(当該為替差益)に係る経済的利得が実現したものとして、当該為替差益は、所得として実現しており、雑所得の金額の計算上、「収入すべき金額」に該当する。
なお、実際の本件各不動産取引による為替差益の有無及び額については、争点2 (為替差益の額を算定する際の外貨の取得時の円換算額の算定方法)についての検討を経る必要があるから、争点2に係る判断の後に改めて検討する(後記3)。
2 争点2 (為替差益の額を算定する際の外貨の取得時の円換算額の算定方法)について
(1)本件外貨建取引に伴い発生した各為替差益に相当する経済的利得の価額は、各取引のために払い出された外貨(ドル又はユーロ)の払出時における円換算額から当該外貨の取得時の円換算額を控除した差額として算定されるが、本件外貨建預金口座への外貨の預入れは複数回にわたっており(前提事実(2)・別表2-1及び2-2参照)、当該外貨の預入れごとに為替レートが異なるため、当該外貨の取得時の円換算額をどのように算定するかが問題となる。
このように、預入れ時の為替レートが異なる外貨が混在している場合において、払い出す外貨の取得時の円換算額をどのように算定するかについては、法において直接の定めはないものの、外貨の性質等を考慮し、基本的には、法定評価方法の中から、適用すべき評価方法を採用するのが合理的である。
(2) 所得税法は、2回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券で雑所得又は譲渡所得の基因となるものを譲渡した場合に係る有価証券の取得費等の計算に関して、総平均法に準ずる方法を採用しているところ(所得税法施行令118条1項)、これは、有価証券はその種類や銘柄の異なるものが一定数存在するものの、一般的な動産である商品や製品とは異なり、物理的な劣化による価値の減少が想定されない上、同一銘柄の有価証券は代替性を有し、その取得時期や取得費等が異なっても一単位ごとに認められる権利や性質、価値などは基本的に変わらないと考えられるので、これらを等価とみて単価を平均する評価方法を適用することとしたものと解される。
そして、外貨も、有価証券と同様、種類の異なるものが一定数存在するものの、物理的な劣化による価値の減少が想定されない上、同一種類の外貨は代替性を有し、取得費等が異なっても一単位ごとに認められる権利や性質、価値などは基本的に変わらないと認められ、有価証券の上記の性質と同様の性質を有するといえるから、2回以上にわたって取得した同一種類の外貨について、為替差益の額を算定する際の取得時の円換算額の算定においては、有価証券と同様に、単価を平均する総平均法に準ずる方法を適用するのが最も合理的である。
したがって、本件各為替差益に係る外貨ー単位当たりの取得時の円換算額の算定においても、総平均法に準ずる方法によることが相当である。
(3) 原告は、暗号資産の取得価額の計算に関する所得税法施行令119条の2 第2項を根拠として、本件各不動産取引に係る部分については、外貨の取得時の円換算額の算定において個別法を用いるべきである旨主張する。
ア確かに、暗号資産は、外貨と同様に、物理的な劣化による価値の減少が想定されず、同一の種別である限り代替性を有し、取得価額が異なっても、ー単位ごとに認められる権利や性質、価値などは変わらないといえるため、外貨と類似の性質を有するということができる。
もっとも、所得税法施行令11 9条の2が、暗号資産の取得価額の計算につき、取得価額を平均化する方法(総平均法又は移動平均法)を原則としつつも(同条1項)、例外として、「暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得」につき、平均化の対象に含めないものとしたのは(同条2項)、暗号資産の中には、全世界的に通貨(外貨を含む。)との交換ができず、特定の暗号資産とのみ交換できるものがあるところ、このような暗号資産の交換等のために一時的に必要となった暗号資産を含めて取得価額の平均化をすることは実態に合わないためであると解される。したがって、同項の規定が適用されるのは、暗号資産の中でも、全世界的に通貨との交換ができないという限られた暗号資産の交換等の場面に限定されると解される。(以上につき、乙2 3、32参照)
イ これを本件各不動産取引についてみると、まず、本件各不動産は、通貨(ドル)と一般的に交換可能である。
そして、原告は、本件借入れ①の直前である平成29年8月31日において、本件外貨建預金口座に5901万8616.04.ドルを保有していたところ(別表2-1・順毎100の⑤欄参照)、この金額は、原告が本件各不動産の取得のために行った本件各送金の総額1437万1436.93 ドルの4 倍を超える金額である(前提事実(2) 、(3)) 。しかも、本件各証 拠によっても、原告が本件各借入れ前に保有していたこれらのドルをもって本件各不動産を購入することができなかったとの客観的な事情は見当たらない。
そうすると、本件各借入金につき、本件各不動産取引のために「一時的に必要」なドルの取得であったということはできない。
ウ原告は、所得税法施行令119条の2第2項の「一時的に必要な」の解釈等に関し、①本件各不動産取引の前から原告が本件各不動産を購入するに足りるドルを保有していたことは「一時的に必要な」取得に該当するか否かの判断に影響を与えない、②???銀行との契約上、本件各借入金を本件各不動産の取得のために用いることが義務付けられていた、③原告が本件各借入れ前から保有していたドルは、外国為替投資事業の結果として保有していたものであり、不動産事業とは区別する必要があり本件各借入れの必要があったなどとして、本件各借入れが同項の「一時的に必要な」ドルの取得である旨主張する。
しかし、暗号資産(A)を購入するために暗号資産(B) を購入する場 合において、当該暗号資産(B)の購入以前から当該暗号資産(A) を購入するに足りる十分な量の暗号資産(B) を有していたときは、当該暗号資産(B) の購入は「一時的に必要なj取得に当たらないと解するのが文理解釈として自然かつ合理的であり、また、為替レートの変動を踏まえた利益操作を防止する観点からも相当である。
さらに、仮に、原告が???銀行との間で、本件各借入金を本件各不動産の取得のために用いる旨の契約上の義務を負っていたとしても、それらの義務は本件各借入れに係る各金銭消費貸借契約を締結したことによって生じたものにすぎず、原告が本件各借入れ前に保有していたドルを本件各不動産の取得のために用いることができなかったことを基礎付ける事情ではない。
しかも、本件各借入金が入金された本件口座は、本件各借入れ及び本件各送金以外の取引にも用いられており(乙1) 、原告が本件各不動産取引と他の取引とで使用する口座を区別していた様子はうかがわれない上、仮に原告が使用する口座につき何らかの区別をしていたとしても、そのような主観的な事情は、本件各借入金が本件各不動産取引のために「一時的に必要」な取得であったことを基礎付ける事情とはいえない。
したがって、原告の上記①から③の主張は、いずれも理由がない。
(4) 小括
以上によれば、本件外貨建取引のうち本件各不動産取引に係る部分についても、所得税法施行令11 9条の2第2項に準じて個別法を用いることはできないというべきであり、本件各為替差益の算定における外貨の取得時の円換算額の算定は、総平均法に準ずる方法によるべきである。
こちらの論文も参考にしてください。
「仮想通貨(暗号通貨、暗号資産)の 譲渡による所得の譲渡所得該当性── アメリカ連邦所得税におけるキャピタルゲイン及び為替差損益の取扱いを手掛かりとして ──」税法学581号
以下の記事も参考にしてください。
✨ 本判決のポイント
為替差益の所得実現(争点1)
外貨が不動産に置き換わることで、その為替差益に相当する経済的価値が確定し所得として実現したと判断された。外貨建借入れの場合と異なり、不動産は外貨から独立した価値を有するため、資産状態の実質的変化が生じたと認められた。
暗号資産の個別法の適用否定(争点2)
暗号資産の個別法(所得税法施行令119条の2第2項)は全世界的に通貨との交換ができない特定の暗号資産の交換の場面に限定されるため、本件外貨に実質的に類推適用することはできない。
総平均法に準ずる方法の採用
外貨は有価証券と同様の性質(代替性あり、物理的劣化なし)を有するため、総平均法に準ずる方法により一単位当たりの取得時の円換算額を算定すべきとされた。
📌 実務上の注意点
外貨建資産(不動産・有価証券等)を購入した場合、為替差益が生じていれば課税対象となる。外貨のみ保有している状態では未実現利得であり課税されないが、不動産等に置き換わった時点で実現する。
外貨の取得原価算定は総平均法に準ずる方法が原則。暗号資産の個別法を流用した申告は認められない可能性がある。
外国為替差益が生じる取引では、取引ごとの為替レートと取得価額の管理が重要。適切な記録がないと申告誤りが生じるリスクがある。